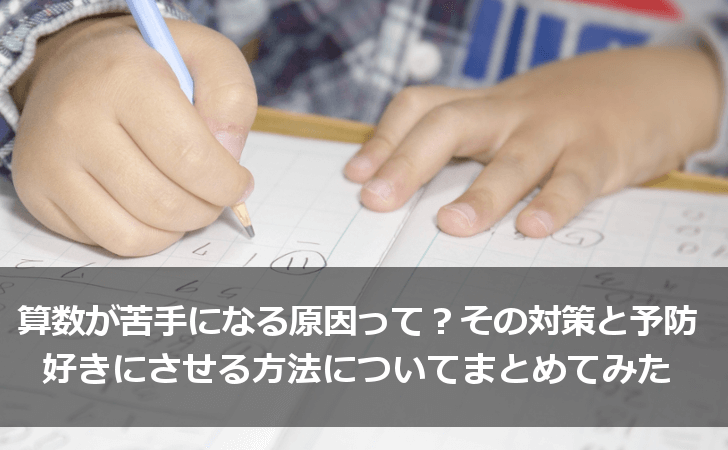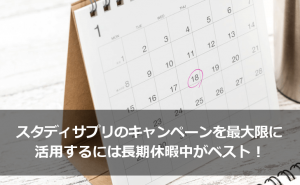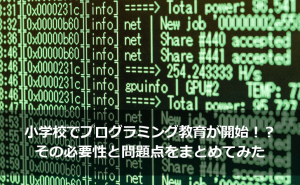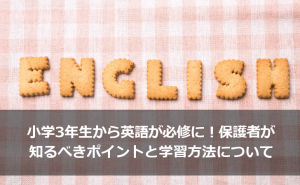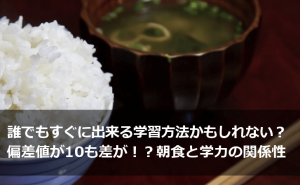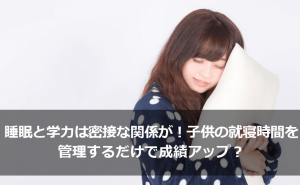私は算数が大好きだったので「どうしてわからないの?考えたらわかるでしょ…」と
つい言ってしまいたくなりますが、人にはどうしても苦手なものってありますよね。
「国語は好きだけど、算数は嫌い」とか、よく聞く言葉なんですが、実は、保護者の接し方次第で「算数好き!」に変えられるかもしれません。
苦手な科目があるという思い込みは、早いうちに解決してあげたいです。ここでは、算数が苦手になる原因や、その対策と予防をご紹介していきます。
[insert page=’common-page’ display=’content’]
算数が苦手になる原因について

「明日、算数が二時間もある…嫌だなぁ。」我が家でよく聴こえてくるセリフです(汗)
「小学、中学、高校、大学…社会人になっても算数は使うよ。」と経験してきた価値観から押し付けてしまいがちです。
まずは何故、算数が苦手と思うのか、原因を見ていきましょう。
[aside type=”warning”] 集中するのが苦手[/aside]
少し考えたらわかる問題でも、苦手意識が先行して集中することができないという子が増えています。
ゲームだったら何時間でも遊んでいるのに、勉強となったらサッパリ…という声をよく耳にします。
難しそう、わからない、退屈…と思うことから、考えることを諦めてしまうんですね。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]これは算数以前に解決しなくてはならないことがありそうです。我が家の娘も同じ事を言っていましたので、そちらの記事も参考にしてくださいね![/voice]
[kanren postid=”5039″]
原因①:計算が苦手
算数は何の問題でも四則計算を使いますよね。
考え方が合っていても、計算ができないとか単純なミスがあるとバツ印をつけらてしまいます。
普段の計算ドリルでも間違ってしまうのに、テストなら尚更緊張して計算間違いしてしまったり…。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]あまりにもミスが続くと「点数が取れない…算数は苦手。」と嫌いになってしまうのも納得の理由ですね。これは大人も同じ事だと思います…[/voice]
原因②:読み解く力が不足
計算はできるけれど、文章問題が苦手という子も多いですよね。
問題を読み解く力がないと、問題を理解することができません。
計算の前に式を立てることすらできない状況になってしまいます。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]国語力も試されるのが算数です。どちらも克服して、興味を持ってほしいところですよね。つまり読解力は算数でも国語でも重要になります。[/voice]
原因③:図形でつまずいてしまう
図形のイメージができないと苦手意識を持ってしまう子が多いです。
小さい頃、積み木やブロックで遊んだのに…と思いますよね。
算数では平面だけでなく立体図形が出てきます。
色んな図形を展開したり折りたたんだりという単元では、想像力が試されます。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]ぜひ正確な答えを導き出せるように、頭の中を柔らかくしておきたいです。想像力を豊かにする為に親が出来る事は、やはり「なんでも答えから伝えるのではなく一緒に考えてみる」という事も当てはまりそうですね![/voice]
原因④:本気を出していない
賢くて理解力もあるはずなのに、どうしてテストの点数が悪いのかな…と話を聞いてみると「授業がつまらない」とか「面白くない」という子もいます。
家で少し予習や復習をしておくと、授業にも積極的に参加できるようになるのですが、わかるようになるやり方がわからないだけかもしれません。
ほんのちょっとしたアドバイスで、ものすごいパワーが溢れてくるタイプかもしれません。
「やりなさい」と言われるとやりたくないとい反抗的な気持ちも潜んでいる可能性がありますね。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]内心では焦りや悩みを感じているかもしれません。普段以上に子供とのコミュニケーションを多く取るなど慎重に対応していく必要がありそうです。[/voice]
苦手意識を持たせない対策(予防)方法とは?

「明日テストなんでしょ!問題集出して!」…なんて私はよく言ってしまいます。
自発的に取り組むようにするには、まず苦手意識を取り除くのが良さそうです。
算数を苦手とさせない対策(予防)方法についていくつか挙げてみます。
予防方法①:子供の全てを受け止める
[aside type=”normal”] 質問は親を頼っている証拠!一緒に取り組む姿勢が◎[/aside]
何度も同じ質問をしてくることもあるかもしれません。
そんな時もイラっとせずに「そうだね、そこの所が難しいよね」などと共感してあげるのがお勧めです。
できないことを否定せずに全てを受け止めてあげると、子供はわからない所を素直に質問しやすくなります。
「どうしてこんなこともわからないの?」という否定的な感情ではなく「どういう所がわからないか教えてくれる?」等と話を聞いてみましょう。
ちょっとした発想の違いだけで、子供なりに考えている様子がわかり、面白い発想に気づくことがありますよ。
答えは一つでも解き方は何通りもあるのが算数の面白さですし、自由な発想を大切にしてあげたいです。
子供の考えていることを尊重してあげることで、自己肯定感が高まります。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]算数など勉強だけでなく、生活についての向き合い方も変わってくる重要な部分です。温かく見守ってあげられると良いですね。[/voice]
予防方法②:考えることを好きになる働きかけ
[aside type=”normal”] 完全に理解するまで教えないとその後も続かない[/aside]
わからないと質問された時に解き方を全て解説したのに、その時しかわかっていない…ということ、ありませんか?
教え方には工夫が必要です。子供自身が答えを導き出せるお手伝いの気持ちで、ヒントを小出しに。ポイントをアドバイスする程度にします。
これを完全に理解するまで繰り返すと、基礎力と応用力が身についてきます。
周りの大人が「こうしたら解けるよ」と完全にやり方を教えてしまうと、考えなくてもわかってしまうんですよね。
ただ、この「わかった」は瞬間的なもので、身に着かないことが多いです。
「わかったような気がする」ではなく、完全にわかった状態にするような教え方をするのがお勧めです。
算数の好きな子は「何としてでも解こう」という熱意があるという特徴があります。
どうにかして自力でやり遂げると、そこには苦労した分、解けた時の喜びが大きいということ知っているんですね。
また、解き方だけを教えるのではなく、自分で考えて覚えて解いた方が学習内容はしっかり定着します。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]算数は退屈なもの…と思わずに、考えた先にある喜びを教えてあげられると良いですね。[/voice]
予防方法③:国語力を高める工夫
[aside type=”normal”] 異なる教科だが関連性は高い[/aside]
国語が苦手な子は文章問題が苦手…ということがあります。
問題の内容を理解できないというのは、算数以前の問題になってしまいます。
まずは音読して、文章を読み飛ばしたりしていないかを確認します。
次に、問題を絵や図にしながら解いていきましょう。
文章問題は単元によって、内容をはっきりと理解すると同時に、パターンが決まっていることも見えてきます。
苦手と思っている算数も絵にして、想像することでわかりやすくなります。
四則計算の何を使えば良いのかや、決まった公式なども絵にすることで、解けるようになってきます。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]視覚から楽しみながら、無理なく覚えていくことで苦手を予防しましょう。[/voice]
算数が好きな子供ってどんな学習をしているの?
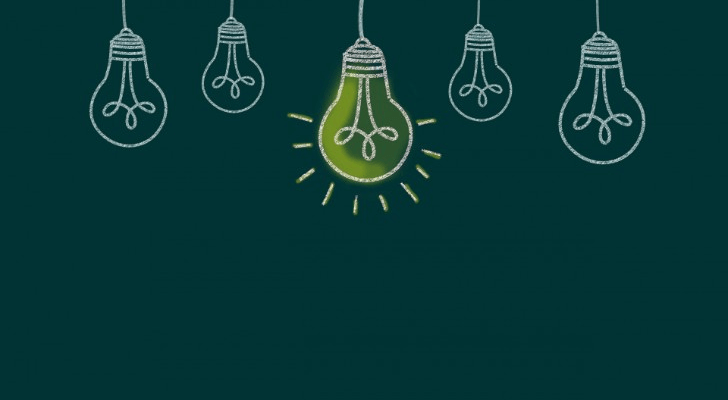
「算数が得意!」家庭で一体どんな学習法を取り入れているのかな?と思いますよね。
塾や家庭教師を利用する方法もありますが、ここでは家庭でも取り組める学習法を見ていきましょう。
学習方法①:パズルや計算ドリルを毎日やる
やはり継続は力なりです。プリント1枚でも構わないので、毎日取り組むことが必要になってきます。
この時、あまり難しすぎる内容でなく、全問正解しそうな位に簡単なものを選びます。
学年にこだわらず、つまずきやすい部分は前の学年に遡って学習することも、時には必要です。
また簡単な計算といえ、大事なステップになります。
確実に基礎力を鍛え、応用問題へ進んでいくうちに点数という結果に表れてくることでしょう。
間違えた時には、冷静に分析する力がついてくるはずです。
やったことがある問題に出会った時には何だか嬉しくなったりと、気持ちに余裕が出てきます。
毎日の積み重ねが自信に繋がる勉強法ですね。
「できた!」という経験を重ねるごとに「私にもできる!」というポジティブな考えに変わっていきます。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]少しずつレベルアップしていくことで、苦手はいつの間にか克服していることと思います。ついついできない所を指摘してしまいがちですが、できたことを沢山ほめて自信をつけてあげましょう。[/voice]
学習方法②:大きな赤丸をつけてあげる
1人で黙々と頑張るのも良いのですが、周りの大人が採点してあげるのがお勧めです。
大人の方がくじけてしまいそうですが、子供のヤル気をアップさせるためには周りのサポートが欠かせません。
間違ってしまった場合にはアドバイスをしながら解き直すようにして、答えが合っている時には大げさかなと思うような赤丸をつけてあげましょう。
「またこの問題を間違えたの?」と叱るばかりでなく「今日は早く解けたわね!」などと褒めるのを忘れないようにすると良いですね。
間違えた問題はどうして間違えたのか、どうしたら正解なのかをしっかりと書き込むようにすると見返した時にわかりやすいです。
ミスしやすい場所、弱点はどこなのかが明確にわかるようになります。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]自分に合った勉強の仕方を見つけることができれば、算数が得意科目になる可能性がありそうです。[/voice]
学習方法③:数の感覚を想像できるような取り組み
生活の中でも簡単なクイズのように、問題を出してみたりと興味を引き出す学習法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
数の大きさや量の多さなどは、生活の身近な所で比べたり計算する場面が出てきます。
我が家では、スーパーに買い物に行ったら「今日のレジは何円かな?」クイズをしています。
ホールケーキはどうやって切り分けたら均等になるか…など、色んな場面で視覚・感覚的に色々と試していると面白さに気づいてくるようです。
実際に絵にしてみたり自分で問題を作ってみたりと発展させていくと、実際の算数の問題で効率の良い解き方がひらめいてきます。
[voice icon=”https://jyukenapps.com/wp-content/uploads/2016/02/benkyoman-150×150.png” name=”勉強マン” type=”l”]基本的な計算をマスターし、数をイメージできるようになると、算数の楽しさを実感し、考える力がついてきます。[/voice]
低価格で算数が好きになる学習方法はご存知ですか?

オンライン学習サービス(勉強アプリ)を使って学習するスタイルが急激に増加しています。
私も娘にタブレット端末を使用したオンライン学習サービスを受けさせている親の一人です。
このタブレット端末やスマートフォンを利用した学習が算数にを好きになる仕掛けが多くあるのはご存知ですか?
突然ですが、あなたのお子様は「一人で勉強」が出来ますか?
「一人で勉強」というのは、自分で机に向かい自分で勉強を始める行為を指します。
ここでは勉強時間は含みません。自らの意思で勉強をする事が出来るかどうかという事になります。
…正直難しいと思います。
受験勉強や、夏休みの宿題といったケースでない場合は、大抵子供は遊びたいものです。
もちろん、我が娘は私がグータラ娘といっている通り机に向かうとすぐに寝てしまう習性がありました(笑)。
まるで、布団に入るかのように…。
オンライン学習サービス(勉強アプリ)の一番の特徴は、「一人で勉強」が出来る事です。
これには色々な理由があるのですが、過去に紹介した事例を参考にしてもらえるとご理解頂けるかと思います。
[kanren postid=”1675″]
そんなオンライン学習サービスをまとめた記事を過去に作成しましたので、こちらも参考にしてくださいね!
[kanren postid=”4121″]