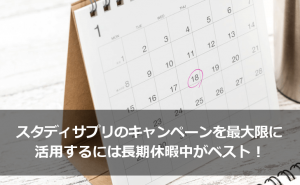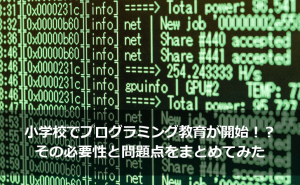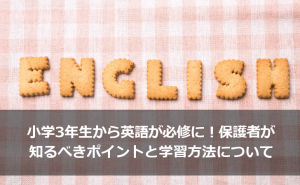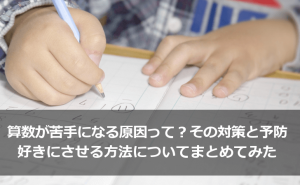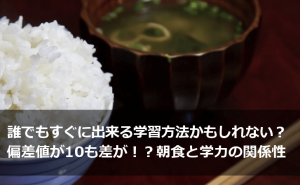新しい学習方法としてオンライン学習塾・予備校が急速に普及しています。
そもそも、今まで鉛筆とノートで勉強していた学習方法と一体なにが異なるのか?
また、ここまで急速に普及した理由とは? 今回はオンライン学習塾・予備校について詳しく解説します!
オンライン学習塾・予備校とは?
インターネット(オンライン)学習サービスは、主に言葉の通りインターネットを通じて学習を行うサービスを指します。
そして、学習塾や予備校の内容に合わせてサービスが展開されています。
今まで書籍として存在していた参考書等はすべてデータ化され、利用者はインターネット上でそれを基に学習します。
全てがシステム化されていますので、利用者の学習状況をデータとして瞬時に数値化する事が可能となっています。 インターネット(オンライン)学習サービスは、ICTを活用した教育サービスとも捉える事が出来ます。
ICT(Information and Communication Technology)は「情報通信技術」の略であり、IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持つが、コンピューター関連の技術をIT、コンピューター技術の活用に着目する場合をICTと、区別して用いる場合もある。国際的にICTが定着していることなどから、日本でも近年ICTがITに代わる言葉として広まりつつある。
引用元:【コトバンク】ICT(アイシーティー)とは
文部科学省が、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の各学校が各教科で教える内容を、学校教育法施行規則の規定を根拠に定めた学習指導要領にもこのICT教育について以下のように記載がありました。
言うならば、IT技術を駆使した新しい学習方法というところでしょうか。
ICT教育という言葉は初耳でしたが、Wikipediaではeラーニングシステムとも記載がありました。
インターネット(オンライン)学習サービスはIT技術の発展によって生まれたもの。
文部科学省が既にそれらを教育方針として盛り込んでいる事自体がオンライン学習の急速な普及を裏付けしていますね。
オンライン学習塾・予備校の特徴
ここまで爆発的にインターネットを通じたサービスを受ける人の割合が増えたのは、そのサービスが社会問題を解決しているという事が背景にあります。
より良い教育をすべての地域の人々に
インターネットの普及によって、誰でもどこにいても様々な情報を得る事が出来るようになったと同じように、 充実した教育を住んでいる地域に関係なく、受ける事が出来るといったのが最大の特徴です。
以前にも紹介しましたが、住んでいる地域によっても大学進学塾や教育のレベルに差がある事はご存じですか?
学習塾における「カリスマ講師」と呼ばれる先生のほとんどは都市部に集中し、かつ学習塾の収益構造の為に一部の生徒のみが授業を受ける事が出来る為に住まいによっては大学進学率や学習レベルに差がある事が報告されています。
住んでいる地域によって大学進学率が異なるというのは、もちろん地理的な要因もありますがそもそも都心と比較して有能な講師の絶対数が少ないという事実も存在あします。
これが、インターネット(オンライン)学習サービスとなれば、動画を再生できるデバイス(PC・タブレット・スマートフォンなど)さえあれば、一流と呼ばれる講師の授業を受ける事が出来るようになったのです!
親の年収による教育格差をなくすために
昨今、日本における格差が大きくなっている事はニュースで取り上げられていますが、 親の年収による子供の教育格差が広がっています。
考えてみれば、それも納得が出来ます。
収入が減れば、生きていくために削れるところから削るはずです。
そして、子供の教育費もその対象となる事が多いのです。 いまや、子供が通う塾の費用は非常に高額になっています。
公立・私立どちらに通っているかによって、費用の大きさや掛かる時期は異なりますが 親としてより良い教育を受けさせたいと思う事から、塾や家庭教師に掛ける費用は多くなりがちです。
ただ、子供に対して費用を掛けられない場合はどうなるのか?
親の年収によって、子供の教育に差が出てしまう現実が今そこにあるのです。
そんな問題もインターネット(オンライン)学習サービスは解決しています。
カリスマ講師の授業内容を録画してそれを配信する事で、コストを削減するとともにより多くの受講生が授業を受けられることが出来るようになっています。
都内に住んでいなくとも、親の年収に関わらず、優良な教育を受ける事ができるのがインターネット(オンライン)学習サービスなんですね!
ICTによる社会の変化が良い循環で生まれているのは、技術が世界を変えているという事が実感できます。
インターネット(オンライン)学習塾・予備校の普及具合
海外ではインターネット(オンライン)学習サービスを使う事が既に主流となりつつあります。 それでは、日本においてはどうでしょうか。
日本で最もメジャーなオンライン学習サービスの1つである「スタディサプリ」においては、会員数が累計有料会員194万人以上・2,900校以上もの学校でサービスが利用されています!
まとめ
インターネット(オンライン)学習サービスは、ITの発展が教育にもたらした1つの変化なんですね。
その変化が今の様々な社会問題を解決していく… まだまだ世の中、捨てたもんじゃないなと思うのは私だけでしょうか(笑)?